公開日:2019年09月24日
マニュアル動画の効果とは?業務効率化につながるメリットや作成のポイントを解説
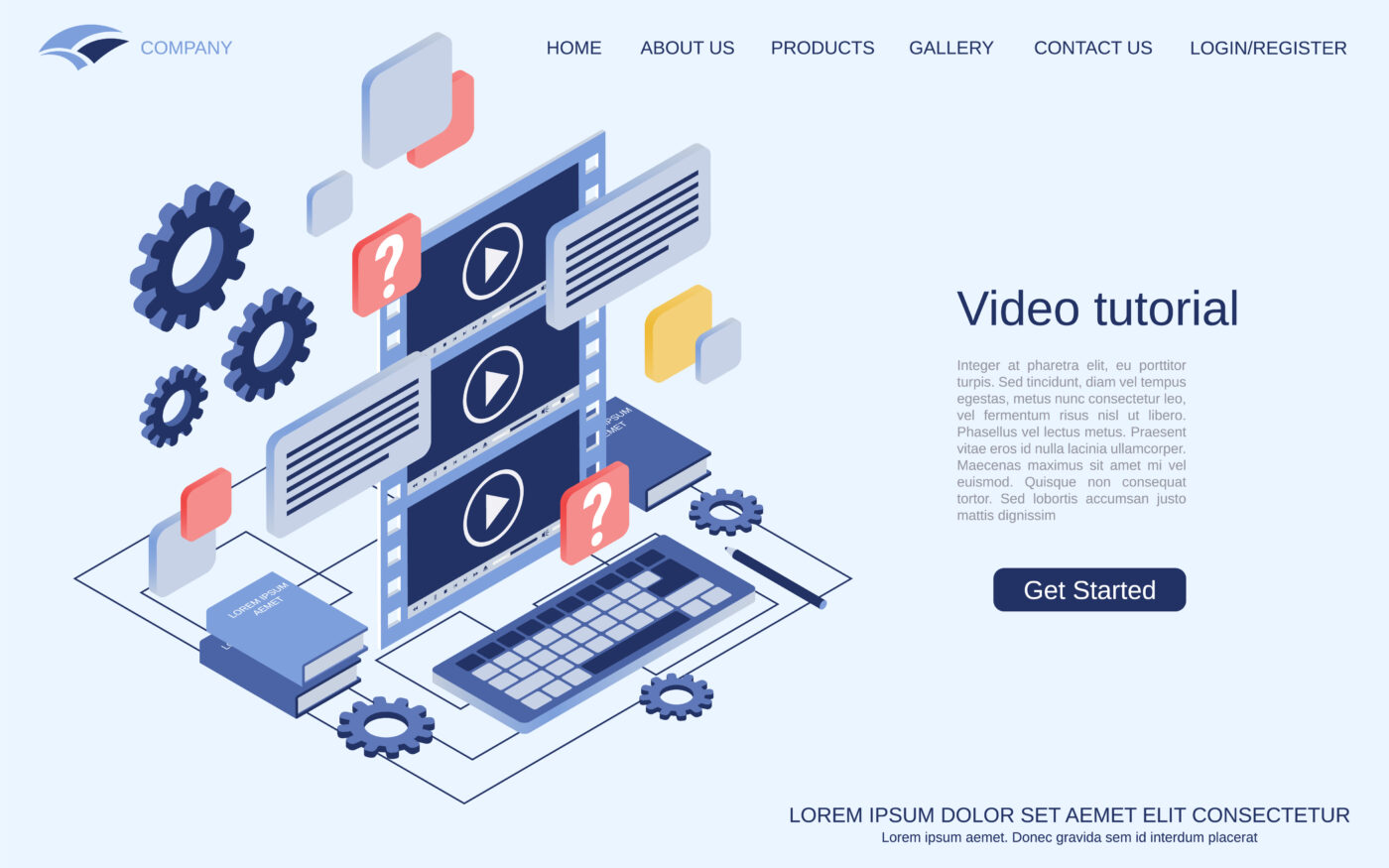
マニュアルや取扱説明書といえば、印刷された冊子やPDFといった形式が一般的でした。しかし、DX(デジタルトランスフォーメーション)の普及にともない、「マニュアル動画」という新しいフォーマットを採用する企業が増えてきています。
紙のマニュアルとの最大の違いは、動きを表現できること。
動画ならではの強みを活かして、紙よりも分かりやすいマニュアルを作ることが可能であり、企業内の業務や社内教育の生産性を上げることができます。
動画制作となると難しい、お金がかかるのでは…と敬遠されがちですが、ポイントを抑えることで自力でマニュアル動画を制作することも可能ですし、中長期的な目線で見ればコストを抑えることも可能です。
この記事では、マニュアル動画の効果やメリット、活用事例、制作時に注意しないといけないポイント、成功させるためのポイントなどマニュアル動画について網羅的に解説します。
この記事の目次
マニュアル動画とは
マニュアル動画とは、業務手順や製品の操作方法などを動画を使って説明するマニュアルです。
従来は紙で作成することが一般的でありましたが、動画活用のニーズが高まり、多くの企業がマニュアルの動画化を採用しています。
動画ならではの映像や音声を活用することで、分かりやすく視覚的に説明できるため、製品やサービスの利用者が手軽に情報を得ることができます。また、社内教育のための業務マニュアルなどといった幅広いシーンで活用されています。
マニュアル動画の効果・メリット
文字情報だけではなく映像や音声があるので、ハードルが低い
文章を読む平均的なスピードは、1分あたり600文字程度と言われています※1。
分厚い紙のマニュアルを受け取り、「これを読んで内容を理解しておいて」と言われる状況。
誰もが一度は経験したことがあるのではないでしょうか。
しかし、読むのに必要な時間がどれだけかかるのかと考えると、辟易したことでしょう。
マニュアル動画は、映像と音声を用いて手順や操作方法を説明するため、文章や写真主体のマニュアルと比べて、学習のハードルが低く、手軽に取り組めます。また、動画であれば再生時間が決まっているため、個人によって異なる読書速度に左右されず、所要時間の短縮や一般化につながるという利点があります。
※1 参考 「速読の理論 あなたの読書スピードと、日本人平均値の関係」SP速読学院
動画なので、動きや手順が分かりやすい
紙媒体のマニュアルの最大のデメリットは、動きを表現できないことにあります。作業手順や複雑な行動、短い時間で様々なアクションを必要とするコンテンツにおいて、紙媒体のマニュアルは最適とは言えません。
動画マニュアルであれば、実際の作業手順を映像化し、見せることが可能です。映像にあわせて自分でも作業を行うことで、複雑な工程でもスムーズに習得することができます。
紙媒体のマニュアルでは時折、「ここの操作手順が知りたいのに、説明が端折られていて分からない。」といった問題が起きました。
しかし、マニュアル動画であればそのような細かいニュアンスも分かりやすく伝えられます。
スマートフォンで閲覧できる
マニュアル動画の利点は、様々なデバイスで閲覧できるという点にもあります。パソコンに限らず、スマートフォンやタブレットでの視聴が可能です。
タブレットやスマートフォンで閲覧できるということは、見る場所を選ばないということ。通勤中の電車の中や、自宅での閲覧も可能です。
コスト削減が可能
動画はファイルとして保存できるため、一度制作し社内のイントラネットに共有さえしてしまえば、印刷費やインク代といったコストも不要となります。
また、マニュアル動画であれば、一度にたくさんの人を教育することができます。
一人ひとり対応する必要がなくなるため、人件費を大きく削減できます。
繰り返し利用が可能
自分の好きな時にいつでも繰り返し確認することができる点もマニュアル動画のメリットの一つです。
動画のチャプター機能を上手く活用すれば、自分の気になる箇所だけを必要な分だけ切り取って視聴できるため、習熟度も大きく向上します。
マニュアル動画の活用シーン

マニュアル動画は、紙のマニュアルを動画化する以外にも様々な活用方法が考えられます。
マニュアル動画を活用できるシーンを紹介していきます。
マーケティングや営業活動での利用
マニュアル動画は、サービスやシステム、ツールの利用方法が解説されているため、機能や特徴の理解を促進する効果があります。
商談時に「こういう使い方は出来るのか」「こういうシーンではどう使えるのか」という質問を受けることは多々ありますが、マニュアル動画を見せることでユーザーの疑問や課題を解消する手助けになります。
また、マニュアル動画が充実していることがわかれば、カスタマーサポートにも力を入れているという意識付けも出来るため、顧客に安心感をもたらします。結果的に顧客の購買意欲を後押しし、商談の受注率が上がるといったマーケティングを有利に進めることが可能です。
業務手順・業務改善での利用
業務手順としての利用もマニュアル動画は有効です。新入社員が入ってきた時にマニュアル動画があれば、短時間で業務の流れや全体像、具体的な作業方法を教えることができます。指導担当も自身の教育負担は減り、自身の業務に集中できます。
また、万が一担当者が部署異動、退職等で入れ替わる時であっても、マニュアル動画があれば、業務の引継ぎもスムーズにできます。
さらには、業務の改善を目的とした活用にも、マニュアル動画は効果的です。業務の流れを動画で確認することで、ボトルネックや改善点を発見することができます。改善点を解決するためのアイデアも出てくるため、業務の生産性向上にもつながります。
社内研修での利用
社員への研修リソースが膨大となり、頭を抱えている人事・営業企画の方は、ぜひマニュアル動画をご検討ください。
教育コンテンツとしてマニュアル動画を制作することで、対面での教育時間を削減することが可能です。また、分からない点が出てきた際も繰り返し閲覧することが出来るため、理解度の向上にも繋がります。
弊社でも、社員研修を動画化することで研修工数を大幅に削減することに成功しています。詳しくは関連記事をご覧ください。
カスタマーサクセスでの利用
ユーザーから受ける「よくある質問」をまとめている企業は多くありますが、ここでもマニュアル動画は活用できます。
操作手順や活用方法をマニュアル動画にして提供することは、カスタマーサポートへの問い合わせ数を減らすことに繋がります。
FAQをまとめたウェブページにマニュアル動画を掲載している企業も増えています。
マニュアル動画の活用事例
ここからは実際にマニュアル動画を活用している企業の事例を種類ごとに紹介します。
製品の操作マニュアル動画
Adobeが提供するPDF編集ソフト「Acrobat」の具体的な使い方を説明しているマニュアル動画です。実際のツール画面を開き、ページの抽出のやり方といった具体的なデモ操作を交えて説明してくれるため、初心者の方も迷わず理解できるようになっています。
また、Adobeはこちらの動画以外にも「画像やテキストの修正の仕方」「スキャン方法」など各操作ごとにマニュアル動画を用意しています。いずれも5分程度の尺でまとめられているので手軽に確認することができます。
業務マニュアル
美容サロンを運営するSA株式会社が社内従業員向けに作成したシャンプーのやり方のマニュアル動画です。
美容師の基本業務であるシャンプーの一連の手順を最初から最後まで丁寧に解説しています。
簡単なように見えて意外に技術力の差が出てしまうシャンプーの気をつけなければならない点も音声だけでなく、テロップも交えて解説しているため非常に理解しやすいです。
動画尺は約20分と少し長いですが、リアルタイムで実演しているため、各手順をどれぐらい時間かければ良いのかもこの動画を見るだけで分かります。
営業マニュアル
こちらの動画はセンチュリー21が接客の質を競う接客グランプリでグランプリを受賞したスタッフの接客ロープレ動画です。
社内全体の営業力を上げるためには、社内で優秀な営業マンの営業風景を見せるのが効果的です。
営業時の話し方や声のトーン、アイスブレイクといった細かい所作も動画であれば吸収しやすいです。
新入社員や既存社員に向けて「取れる営業の実践的なマニュアル」として活用すると良いでしょう。
マニュアル動画の制作パターン
マニュアル動画は大きく分けて2つのパターンに分類できます。
手順を撮影した動画
画面や作業を撮影し、ナレーションやテロップで解説するパターンのマニュアル動画です。
人が解説する動画
映像にあわせて解説するというスタイルは同じですが、ナレーターではなく、実在の人物が解説を行うスタイルです。
テレビ番組や講義のようなイメージで視聴ができるフォーマットです。
マニュアル動画の制作の手順
マニュアル動画の制作手順については。以下の6つの手順を踏みます。
- 目的・ターゲットを決める
- 構成案を作成
- 台本を作成
- 動画の撮影・録音を行う
- ナレーションを入れる
- 編集をする
きちんと手順を踏まえないと制作に大きな時間を要してしまったり、良いマニュアル動画の完成ができなくなるため、きちんと押さえましょう。
目的・ターゲットを決める
まず、マニュアル動画を作るときは、動画を作る目的と誰をターゲットとするのかを決めましょう。
消費者に向けてなのか、社員に向けてなのか、取引先に向けてなのか、ターゲットを誰にするかで、そもそもの動画の内容や言葉の使い方も変わってきます。
例えば、社員向けの教育マニュアル動画を作る場合でも、新卒社員向けなのか、入社3年目の社員が対象なのかでも、そもそも基本的な知識の理解度が違います。
ターゲットを明確にすることで、どんなコンテンツが必要なのか、どういった言葉を使えばいいのかなどがわかります。まずは誰に向けて動画マニュアルを作るのか考えてみましょう。
以下の点に注意して目的・ターゲットを決めると良いです。
・ターゲットは誰か
・ターゲットの理解度はどうか
・ターゲットが求めているトピックは何か
・ターゲットの再生環境はどうか(PCなのか、スマホなのか)
・動画視聴後のターゲットはどんな状態になっているか
構成を作成
次に動画の構成を決めましょう。マニュアルを通してターゲットに伝えたい内容は何なのか、注意点は何か、箇条書きで良いのでピックアップします。
これをしておくことで次の台本を作成する時に、情報の抜けモレを防ぐことができます。
もし、既存の紙マニュアルがあるのであれば、それをベースに1項目ずつ目次を作ると作成しやすいです。
紙マニュアルでは実際に説明不足だと感じている点を整理しておけば、その箇所を掘り下げて説明するパートを設けるといった構成も作れるので、既存の紙マニュアルよりもよいマニュアルが作れます。
台本を作成
構成が完成したら、台本作成になります。これはテキストベースでも絵コンテを作るでもかまいません。
台本を用意しておけば、全体の流れを把握した上で撮影にのぞめます。無駄な撮り直しも防げます。
動画の撮影を行う
台本が完成したらいよいよ動画の撮影になります。
動画の内容によって撮影方法も変わってきます。
例えば商品やサービスのチュートリアル動画であれば、実際のデモ操作画面を撮影、録画すればよいです。
一方で研修動画マニュアルの場合は、実際に人がカメラに向かって解説を行うケースが多いため、人や場所の確保、機材の手配が必要となります。
台本が完成したタイミングできちんと準備しておきましょう。
また、撮影時のポイントとしては同じシーンの撮影でも、様々なアングルから撮影しておくことをおすすめします。
アングル次第で内容の伝わりやすさが変わってくることがあるため、撮り直しのリスクを防ぐことができます。
ナレーションを入れる
ナレーションが必要な場合はこのタイミングで収録を行います。
ナレーションがあることで、動画の全体像や動画内にあるイラスト、図表の説明がしやすくなります。
ユーザーにとってもより理解しやすいマニュアル動画となるでしょう。
ナレーションの収録にあたっては、事前にナレーターとの打ち合わせが必要です。
ナレーションのスピードや抑揚についてすり合わせるために、早めに台本を渡しておきましょう。
編集をする
撮影、ナレーションの収録といった素材が揃ったら、いよいよそれらの素材を一つにつなぎ合わせるという編集作業となります。
一般的に業務手順を示すマニュアル動画となると、事務的な説明になるため冗長化しやすくなります。
BGMやテロップなどを使って見やすさを意識し、短時間で簡潔な動画編集を心がけましょう。
編集を一通り終えたら、編集内容に問題がないか見直しましょう。
また、自分で見返した後に第三者からフィードバックをもらうことで、客観的な意見が得られるので、より最終的な完成度を高めることができます。
マニュアル動画制作時に注意するポイント

多くのメリットがあるマニュアル動画ですが、やみくもに制作するのはオススメしません。制作にも工数がかかりますし、外注するのであればコストが発生します。
工数に見合う効果を期待するのであれば、制作内容を入念に検討することが必要です。
具体的に3つのポイントを取り上げます。
音声が再生できない環境を想定する
様々なデバイス・環境で視聴できるので、音声を聞くことができない環境を想定してマニュアル動画を制作しましょう。
音声にあわせてテキスト(テロップ)を挿入することが解決方法になります。
映像にする部分と文字・音声で伝える部分を切り分ける
全てを映像にしようとすると、映像の時間が長くなりがちです。文字情報や図表で解説できる部分がある場合は、組み合わせて構成することを検討すべきです。
製品の導入手順を説明するのであれば、フローを図に起こして提示することが有用です。言葉で説明するよりも、フローチャートを明示するほうが、視覚的に理解を促すことができます。
マニュアルにするテーマを細分化し、短いものを複数作る
マニュアル動画に関しては長い動画を1本作るより、短いものを複数作る方が良いとされています。
ユーザーが求めていることは、限定的です。一つの動画で1から10まで説明する必要はありません。テーマを細分化し、短い時間で端的に伝える動画を目指しましょう。
テーマを分けることで、ユーザーニーズに合わせて適切なマニュアル動画を提供することが出来るようになります。また、編集工数も少なくなるため、リリースのスパンが短くなります。
動画尺は5分程度に収めるとユーザーとしては、気軽に動画を確認でき、繰り返し視聴できるでしょう。
マニュアル動画を更に活用するための方法
マニュアル動画は作って終わりではありません。ユーザーに使ってもらってはじめて効果が生まれるコンテンツです。そのため、「どう使ってもらうのか」「使ってみた効果はどうだったのか」を検討する必要があります。
マニュアル動画単体では効果検証ができない
マニュアル動画に限ったことではありませんが、その動画を見て、実際に疑問が解決できたのか、あるいは理解度が上がったのか、ということを検証することは難しいのが現実です。
視聴率、再生時間といったデータを計測することで大まかな分析はできますが、実際にユーザーのためになったのかはアンケート調査などが必要になります。
インタラクティブ動画なら、より詳細なデータを取得可能
インタラクティブ動画とは、動画内をタップできるようにすることで、ユーザーの見たいコンテンツを選択したり、フォームに回答してもらったりすることが出来る、新しい動画のフォーマットです。
例えば、動画内に「この説明で理解できましたか?」といった設問を行い、「はい」であれば疑問解消、「いいえ」であれば更に細かい説明を促すコンテンツを表示する、という導線設計を、1つの動画で行うことができます。
インタラクティブ動画以外でこうした導線を実現するためには、ウェブページでの設計や配信プラットフォームの構築が必要になりますが、1本の動画で気軽に検証ができるのがインタラクティブ動画のメリットです。
ユーザーがどういった選択肢をタップしているのかというデータが収集できるため、制作したマニュアル動画の効果検証を行い、動画自体を改修したり、不足しているコンテンツを制作したりと、PDCAを回すことが出来るようになります。
弊社でもインタラクティブ動画を活用してコンプライアンス研修を行い、工数を削減&研修の改善を行っています。詳しいデータは以下の資料でご紹介していますので、気になる方はぜひダウンロードしてみてください。
まとめ
マニュアル動画は従来の紙マニュアルでは伝えきれなかった細かいニュアンスも、動きや音声を使って、短時間で多くのことを伝えることができます。
また、マニュアルを動画化することで教育担当の人的リソースやコスト面の削減も期待できます。
しかし、クオリティの高いマニュアル動画を制作するにはきちんと目的やターゲットを明確にした上で制作しなければなりませんし、制作後もきちんと効果検証をする必要があります。
Videoクラウドでは、実際に当社自身がマニュアルを動画化して業務効率化をした経験を元に、企業のDX化を支援させていただきます。
