公開日:2022年12月12日
採用動画の効果とは?種類やトレンド・活用事例を紹介

「採用動画って効果あるの?」
「採用動画は制作コストも高いし、手間もかかりそう、、」
採用動画に対してそのようなイメージをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実際、近年では、新卒・中途採用問わず、採用活動において採用動画を活用する企業が増えています。
今回は採用動画が具体的にどのような効果をもたらすのか、採用動画の種類や活用シーン、また採用動画の制作や活用する上での大事なポイントなどを解説していきます。
この記事の目次
採用動画とは
採用動画とは、企業の経営理念や仕事内容、職場の様子、魅力などを動画にまとめたものです。
企業は求職者が採用動画の視聴により、自社への理解を深め、会社説明会や選考へエントリーしてもらうことを期待しています。
従来の採用活動では紙ベースの資料を使って自社の説明をしていました。
しかし、実際どのような仕事をやるのか、職場の雰囲気などは温度感をもって説明しづらいものがありました。
ただ、採用動画であれば仕事内容も職場の雰囲気も実際の一連を感覚的に見せることができます。
採用動画の効果・メリット
それでは、採用動画は具体的にどのような効果をもたらすのかを見ていきます。
主な効果は4つです。
①志望度・理解度の向上
まずは志望度・理解度の向上です。
採用を成功させるには母集団形成を行わなければなりませんが、この母集団形成が採用活動において一番難しい課題です。
母集団形成には求職者に自社のことをしっかりと理解してもらうことが大切です。
求職者が就職先、転職先に求めていることに対し共感できるような動画を制作すれば、自社に対する理解度や志望度の向上が見込めます。
実際に弊社が過去応募者に行った調査では、採用動画の視聴後、志望度が向上したという人が8割以上もいたことが分かりました。
②イメージ向上
企業イメージの向上にも効果が見込めます。
採用動画には求職者に自社がどれだけ良い会社なのか、長所やアピールポイントがまとまっています。企業の経営理念やこれまでの実績、働いている従業員、社会活動など企業の魅力をしっかりとアピールすることで、より優秀な人材の獲得にもつながります。
③ミスマッチの防止
ミスマッチによる早期離職は決して少なくありません。時間やコストなど労力をかけて採用したとしても、「思っていたイメージと違う」という理由で早期離職されてしまうケースも多々あります。
しかし、動画であれば、従来説明しづらかった実際の仕事のやり方や一日の動きなども一連の流れで分かり、働いている人の表情や様子も生の声つきで分かります。
採用動画を見れば、入社後にイメージが違ったというミスマッチは防げるでしょう。
また、逆に現場のリアルな様子を見せることで、
「こういう仕事がしたかった」
「このような雰囲気で働きたい」
「こんなオフィスで働きたい」
といった志望者が増えるかもしれません。
④採用業務の効率化
採用動画の活用は求職者側だけでなく、採用する企業側にもメリットがあります。
これまでの採用活動の会社説明の方法としては、採用担当者が求職者一人ひとり個別で対応したり、会場を用意して説明会を開催していました。
このやり方では、説明会に割く時間もコストも開催される度にかかってしまう、というデメリットがありました。
会場をおさえる費用や資料の印刷代、交通費など諸々かかり、何より担当者が通常業務に追われ、説明会資料作成の準備にリソースを割けないという問題がありました。
しかし、採用動画であれば、初期制作費用はかかるものの、一度作成さえすれば何度でも活用することができます。
また、動画であれはオンラインでも視聴が可能となるため、会場費や印刷代も不要となります。
さらに、毎度資料の準備を行う必要もなくなるため、工数も大幅に削減できるようになります。
実際当社の採用活動でも動画を取り入れたことで面接時間を60時間も削減することができました。
こちらについて詳しく知りたい方は下記の記事を見てください。
採用動画の種類

次に採用動画の種類について紹介していきます。
ブランディング動画
ブランディング動画とは、企業のブランドイメージや商品・サービスのコンセプトや世界観を伝える動画です。
音楽や風景、人物を駆使し、ブランド「らしさ」を直感的に求職者に訴えます。
採用活動におけるブランディング動画の目的は「企業」と「求職者」をつなぐこと。
すなわち認知度の向上です。
求職者の印象に残るブランディング動画は企業の信頼度や将来性を伝えることができるため、求職者の志望度を高めることもできるでしょう。
インタビュー動画
実際に企業で働く社員や企業の社長が直接インタビューに応じる様子を組み込んだ動画も採用動画の1つです。
実際に「どのような仕事をしているのか」「仕事のやりがいは何か」「実際の社内の雰囲気はどうなのか」など実際入社してからではないと分からない情報や現場の社員だからこそ言える情報を答えることで、求職者が入社した後のイメージがしやすくなり、安心感を与えられます。
昨今の求職者はリアリティのある情報を求めているため、その点インタビュー動画は効果的です。
会社説明動画
会社説明動画は文字通り、企業理念や沿革、主な実績、求人の募集要項など会社の情報を総合的に説明します。
最も採用活動で使われている形式の採用動画です。
ブランディング動画やインタビュー動画に比べて、より具体的に求職者が求めている情報を一つ一つ順番に説明しています。
また、「実際の選考中によく聞かれる質問」や「企業がどのような人物像を求めているのか」などを動画内に組み込んでおくのも効果的です。
求職者目線でいうと、選考前に事前に動画を見て解消できる内容であれば、面接中に質問する必要もなくなり、企業が求める人物像が分かっていればその人物像に対して自分が何ができるのかアピールすることができます。
企業者目線でいうと、自社の説明工数が減り、その分より求職者自身についてヒアリングをする時間が作れます。
会社説明動画は実際の選考活動を円滑に進めるための大きなサポートツールです。
選考フローの最初に組み込むことをおすすめします。
採用動画のトレンド

採用動画のトレンドはリアリティのある情報を取り入れることと、求職者とコミュニケーションを取ることです。
トレンドとなっている採用動画の形式を5つ紹介します。
①インタラクティブ動画
インタラクティブ動画とは動画内にタッチポイントを設置し、視聴者の選択によって動画のストーリーや内容が分岐する動画です。
これまでの動画は発信者側が視聴者側に一方的に情報を発信することしかできませんでしたが、インタラクティブ動画は視聴者側が主体的に動画視聴に参加できます。
求職者にとってインタラクティブ動画は、自分自身の選択で自分の知りたい情報のみを無駄なく効率よく得ることができます。
②ドキュメンタリー動画
実際の従業員1人にフォーカスしたドキュメンタリー動画も採用動画のトレンドの一つです。
ドキュメンタリー形式にすることで朝会社に出社してから、仕事を終え、退社するまでの実際の一日の様子を知ることができます。
どのような仕事を、どのような環境で、どのような格好でなど多くのリアルな情報を自然なかたちで知ることができます。
求職者としては、入社後の自分の働いているイメージをより明確にできるでしょう。
③座談会形式の本音動画
社員同士が集まって座談会形式で会社についてのリアルを話し合う本音動画もトレンドです。
座談会で話し合うテーマについては、求職者が面接の場では聞きづらい内容にすると効果的です。
例えば、収入面や残業、有給といった就業時間面などです。
通常、企業側が情報を伏せがちな内容をあえてさらけ出すことで、求職者は「隠し事をしないオープンな社風」と捉えられるため、かえって信用を得られるというメリットがあります。
入社後にイメージが違ったというミスマッチも防止できます。
④ドローンを活用した動画
ドローン技術が発展したことにより、ドローン撮影を活用する動画も増えています。
特にドローンを活用したオフィス紹介動画は、普段の人の目線からは見ることができない視点からオフィス内の映像や人の表情などを映すことができるため、ダイナミックな演出ができます。
また、ドローンによる撮影動画は編集にこだわらずとも、ドローン特有の視点を映すだけで十分魅力的な臨場感のある動画に仕上がるため、制作コストを抑えられるというメリットがあります。
⑤縦型動画
スマホでの視聴再生に最適化した縦型動画は今一番のトレンドと言えるでしょう。
「YouTubeショート」「Instagramリール」や「TikTok」など縦型動画に特化したプラットフォームが普及し、20代の若い世代はこれらのSNSを非常に多く利用しています。
ユニークな動画が作成できれば、若い求職者の間で話題を呼び、シェアされます。
結果的にエントリー数の増加も期待できるでしょう。
縦型動画の方が横型動画よりも視聴完了率が90%高いというデータもあります。※2
※2 出典:The Rise of Vertical Video Content on Social Media|Spiceworks
採用動画の導入企業が増えている背景
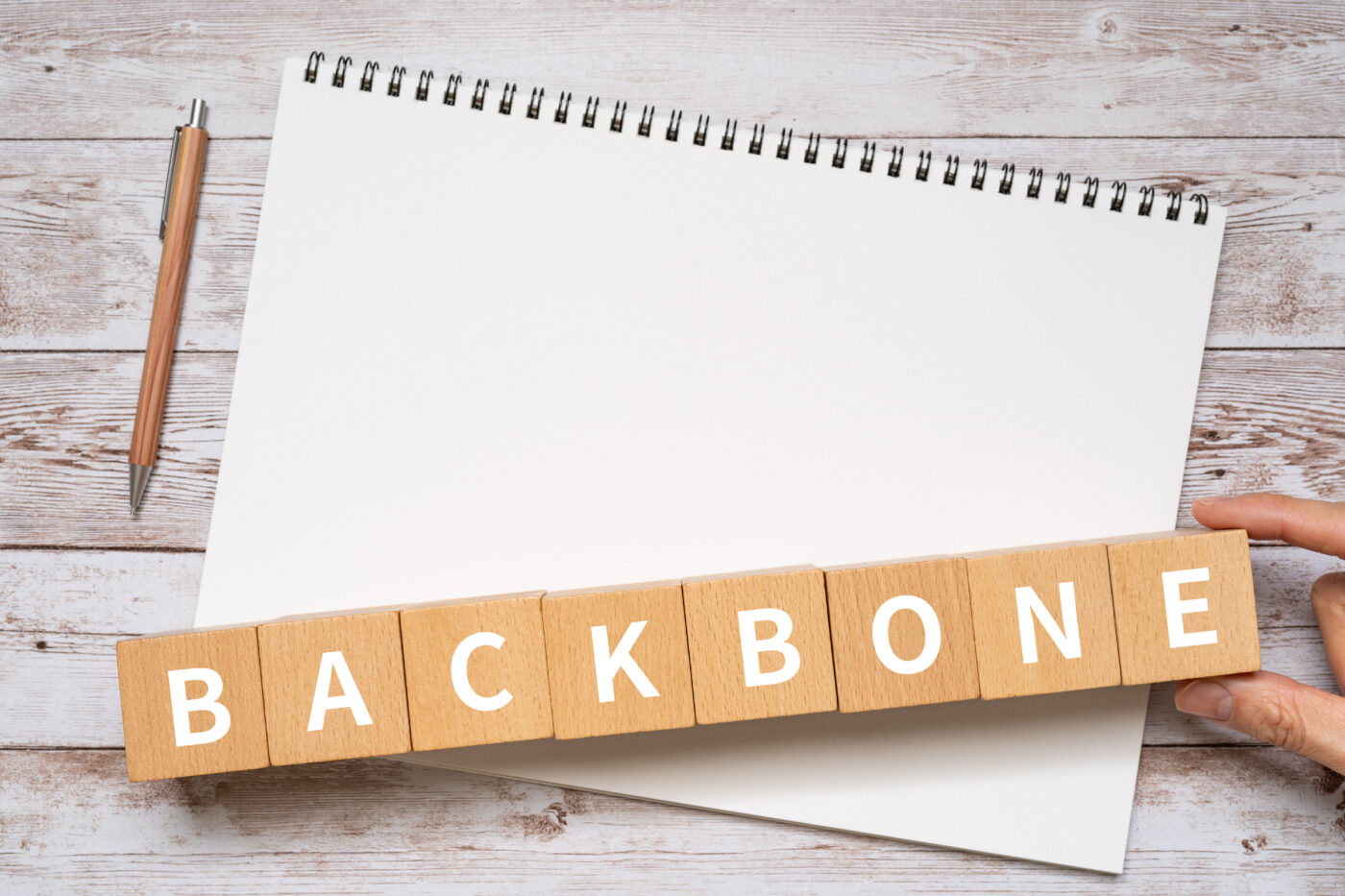
採用動画を取り入れる企業が増えてきた背景としては以下のものが挙げられます。
- 売り手市場
- オンラインでのコミュニケーションが主流化
- SNS、オウンドメディアの活用が活発化
- 求職者のニーズが変化
それぞれ見ていきましょう。
売り手市場
採用活動は企業が人材不足の解消やより優秀な人材を獲得するために行う活動です。
厚労省の最新データによると有効求人倍率は1.35倍(2023年1月時点)でした。※3
ここ数年はずっと有効求人倍率が1倍以上と売り手市場が続いています。
つまり、求職者側が企業を選べるという有利な立場にあるため、企業は自社を選んでもらうためには、これまで以上に自社の魅力をより正確に、効果的に発信する必要が出てきました。
ウェブで採用活動を活発化する企業が増え、コンテンツを充足する目的で採用動画の重要性が増しています。
※3 出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和5年1月分)について」
オンラインでのコミュニケーションが主流化
昨今の感染症の影響もあり、採用活動のリモート化が進んだのも理由の一つに挙げられます。
今ではすっかりリモートワークが定着し、オンラインでのコミュニケーションが主流となりました。
会社説明会や面接をオンラインで行う企業が増えています。
例えば、会社説明を動画化することで下記のようなフローが可能となりました。
STEP1 会社説明動画をまず見てもらう
STEP2 視聴完了後に採用担当が補足説明を行う
結果、採用担当は口頭で1から全てを説明する必要がなくなり、対応リソースの時短、生産性の向上につながります。
また、担当のその時々のテンションで説明内容が変わるということがなくなり、説明の粒度の均一化ができるようになりました。
SNS、オウンドメディアの活用が活発化
動画機能を備えたSNSが普及したことも理由の一つです。SNSの動画広告を利用する企業も増えてきました。
SNSは拡散性が高いという特徴があります。仮に発信した採用動画がある求職者に刺さった場合、その求職者が更にその動画を拡散してくれる可能性があります。
また、オウンドメディアを使って自社の情報を発信する企業も増えてきました。
オウンドメディアは外部の求人媒体と異なり、自社で運用するため、動画コンテンツの発信もしやすいです。
特に最近では、自社の採用サイトだけでなく、Wantedlyやnoteといった既に用意されたプラットフォームで、簡単にオウンドメディアを作成することができます。
外部の求人媒体だと画像とテキストによる募集要項の発信が中心となり、そもそも動画コンテンツの発信がしづらいという点がありました。
しかし、オウンドメディアは自社のブランドイメージを高める情報を発信する場であるため、採用動画とも相性が良いです。
求職者のニーズの変化
最後に求職者のニーズの変化が挙げられます。
求職者は企業の社風や社員の声、オフィスはどんな環境なのかなどの事実情報に加えて、「リアリティ」のある情報を求めるようになりました。
求職者がリアルな情報を求めるのは、自分に合う職場環境なのか、自分のスキルや経験を生かせる仕事なのかどうかを知りたいからです。
求職者のニースは当然個人差はあるものの、
「入社後、収入を上げていくことはできるのか」
「そのための明確な評価制度はあるのか」
「未経験でもやっていけるのか」
「残業は実際のところ多いのか」
こういったリアリティのある情報は求職者が気になるところです。
特に昨今ではコロナを契機に柔軟な働き方ができるかどうかを気にする人も増えています。
採用動画であれば、経営者や現場で働いている社員の声をインタビュー形式で発信できます。また、実際のオフィス環境も映像を通して紹介することができます。
採用動画の掲載場所3選
①企業の採用ページ
コーポレートサイトに加えて、採用向けの専用サイトを設けている企業が増えています。
採用ページに訪問しているユーザーが対象となるため、既に自社への関心が一定以上あると思われますが、更に自社への理解を深めてもらうために採用動画を設置しておくことは効果的です。
採用サイト上にある募集要項の文面だけでは伝えきれない情報を補うことができます。
②新卒エントリーサイトや求人サイト
外部の求人サイトの企業ページでは動画の掲載が可能なところも増えています。
文章や画像に加えて、動画を掲載すれば、他社との差別化もでき、わかりやすく伝わります。
一定以上の関心のある人材が閲覧する企業の採用ページと比べて、外部の求人サイトの方がより多くの求職者に見てもらえる可能性が高いです。
③企業の公式SNS
SNSは拡散効果もあるので、インパクトのある動画や気になる動画があれば、就活生の間でシェアしてもらうこともでき、企業に興味を持ってくれる人を増やすことが可能です。
企業の公式SNSを作成し、企業の情報や採用情報などとともに動画をアップしていくことも有効です。
一昔前は就職活動は求人媒体から求人情報を探したり、エージェントを介して情報を得ることが大半でしたが、今はSNSを活用して情報を手に入れる求職者も多くなっています。
採用動画の活用事例
星野リゾート
一人の女性社員の一日の仕事に密着したドキュメンタリー風に仕立てた動画です。
この動画の特徴としては字幕やテロップはほぼ加えられていません。空撮を駆使して、秋の色づく京都の風景とともに星野リゾートが提供する質の高いサービスの世界観を伝えています。
特に観光・宿泊業も規制緩和により有効求人数が増加傾向にあるため、その中から自社を選んでもらうためには、より自社の魅力を伝える採用動画の活用は効果的といえます。
サイボウズ
こちらは就職先、転職先の候補としてサイボウズを入れている全ての求職者に向けた会社説明動画です。
スライドと共に会社の理念や組織文化、事業内容、給与や評価制度などの総合的な情報を説明しています。基本的なことはこの動画を視聴することで得ることができます。
求職者は選考を受ける前に視聴しておくことで、選考の際に追加で質問したい内容もおさえることができます。
また、企業側にとっても担当者のレベルによって説明内容に差が出なくなり、直接求職者に口頭で説明する必要もなくなります。工数削減という面でもメリットがあります。
ヤフー
ヤフーのオフィス紹介動画です。実際にオフィス内を歩く目線で撮影しているので、オフィスの広さも体感できます。また、執務エリアに関しても「フリーアドレス」、「チーム専用」、「個別集中スペース」など多様なコンセプトがあり、その日自分が働きたいスタイルに合わせて執務スペースを選択できます。
このような空間で働きたいと考えている求職者に対しては、選考へのエントリーや内定承諾への一つ後押しとなるかもしれません。
採用動画の制作手順
採用動画の制作には完成させるまでに大きく下記の4つの工程を踏みます。
- 企画
- 構成
- 撮影
- 編集
各工程で行うことを予め把握しておくことで、準備しておかなければならないことも分かるため、きちんと押さえておきましょう。
企画
まずは、企画です。
採用動画のターゲット、コンセプトを決めましょう。
採用ターゲットが新卒対象の学生なのか、転職希望の中途キャリア向けなのかでも採用動画の方向性は大きく変わってきます。
例えば、新卒採用向けの動画を作るのであれば、自社の新卒入社した若手社員のインタビュー動画を盛り込むとよいでしょう。
同じ立場で入社した先輩がどのようなキャリアを歩んでいるのか、具体的にイメージができるため、就活生の共感を得やすいです。
この企画の工程できちんと採用したい人物像、ペルソナを設計することで動画の方向性が明確になります。
構成
動画の方向性が決まったら、次は具体的に動画の構成を作ります。
求職者に伝えたい内容、アピールポイントをピックアップし、どのような順序で伝えるか動画の構成を組み立てていきます。
構成は絵コンテを作ることをおすすめします。
絵コンテがあれば、動画の全体の流れが把握できるようになるため、この後の撮影がスムーズです。
撮影
構成が完成したら、いよいよ撮影に入ります。
撮影は制作する動画の内容によって、手配するスタッフの数、撮影期間なども大きく変わってきます。
各関係者のスケジュール調整は構成ができたタイミングできちんと行っておきましょう。
また、屋外での撮影を予定している場合は撮影日当日の天候にも気をつけなければなりません。
万が一、撮影日が悪天候で撮影が延期になることも想定し、予備日を踏まえたスケジュール調整をしましょう。
編集
撮影が終わったら、撮影した素材を一つの動画に繋げる編集作業になります。
BGMやテロップなどを使って、求職者にアピールしたい内容を分かりやすく、端的に伝えられる編集を心がけましょう。
また、採用動画をどこで発信するかで最適な動画尺や形式も変わります。
動画を公開する場所に合わせた編集をしましょう。
ン(企画)の段階からプロに依頼することをおすすめします。
採用動画制作を成功させるポイント
採用動画の制作を成功させるにはどのような点を押さえておけば良いか、ポイントをいくつか紹介します。
利用目的の明確化
採用動画は利用目的ごとに伝えたい内容も変わるため、制作前にどのように活用していきたいかを明確化させることは必須です。
新卒向けか中途向けかでも伝えたい内容は全然違うため、同じ動画は使えません。
会社のことを知っている人か、まだ知らない人に向けて発信するのかでも内容は変わります。
また、募集している職種によってもターゲットは変わってくるでしょう。
そのため、採用動画は採用したい人物像に合わせて、それぞれ動画を制作しなければなりません。
適切な発信先の選択
動画を発信できる場は多様にあります。
SNSをとってもYouTubeやTwitterでも利用層は違いますし、メディアの特性も違います。
また、広告掲載する場合は出稿の規定もそれぞれ違うため、それぞれに合わせた内容や長さの動画を作りましょう。
ポジティブな面でなく現実も伝える
企業としては、自社にエントリーしてもらう人を増やすために、自分の会社の良いところをたくさんアピールしたいところです。
しかし、ポジティブな面ばかりを盛り込んでしまうと、実際の職場環境とのギャップによって、入社後に不満を持ち、早期離職してしまう人もいます。
ミスマッチを防ぐためには、良いところばかりではなく、実際の仕事の現実も見せることが必要です。
リアリティのある情報を伝えることで企業に対する信用度は上がるでしょう。
採用活動全体に組み込む
作成した採用動画を自社サイトや求人サイトに掲載してただ見てもらうことを待つだけではなく、会社説明会や面接といった実際の採用選考フローの中にも採用動画を見てもらう機会を組み込むことも大事です。
採用動画には志望者に対し、自社への理解をより向上させる効果があり、内定承諾率のアップも期待できます。
また、会社説明を動画で行えば、求職者一人に対する対応リソースも大幅に削減できるため、その浮いた時間で今まで以上に多くの志望者と接触する機会を設けることができます。
より優秀な人材との出会いが多くなるかもしれません。
まとめ
採用動画は採用活動を行う企業にとって、求職者に自社の魅力を伝えるツールとして非常に有用であることが分かりました。
とはいってもこれまで動画の制作なんてしたことがなく、ハードルが高いという方もいらっしゃるかと思います。
Videoクラウドではこれまでに数多くの企業様の採用動画を制作してきました。
採用動画の制作をご検討の方はお気軽にVideoクラウドまでお問い合わせ下さい。
